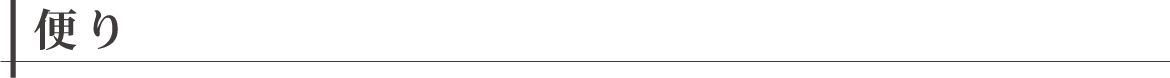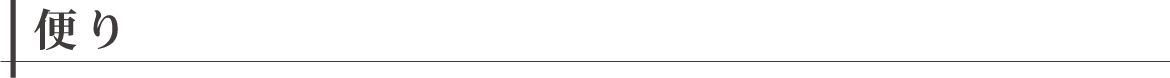
南相馬修道院からの便り
「再創造」

15回目の3.11
毎年、繰り返してこの日を記念していますが、
いつも思うのは、神様は、この大きな災害を通して私たちに何を語っておられるのかということです。
あの日多くの人が、神も仏もあるものか、どうしてこんなことが自分の身に起こったのか?
という思いを抱いたことでしょう。本当に神様は何を語っておられるのでしょうか?
日本は災害大国で、昔から、災害によって互いに助け合う精神的風土が培われてきました。
日本人の忍耐強さと、打たれても打たれても立ち上がっていく不屈の精神、
互いを思いやり、調和を大切にする和の精神は外国の人からも高く評価されています。
しかし、この地域災害、3.11は、それまでの災害とは違った様相を呈しています。
自然災害の上に人的なミスと嘘と政治的な虚偽と責任逃れとが複雑に絡んだ災害です。
やり場のない怒り、金銭的な補償で解決するものでもない理不尽さ、
本当にこの地に居て、私たちまで苦しい思いをします。
長い時間がたてば心が晴れるようなものでもないのです。
でも、その中でみんな懸命に生き、再創造の命、再創造の人生、再創造の生業、
再創造の街づくりに力を尽くしておられる姿に感心し、心から頭が下がる思いです。
先月紹介した、小高夏季自由大学で小高の町にこんなものがあれば・・・と提案された事柄を見てもらうと、
小高の復興はまだまだ道半ばだということがわかっていただけるでしょう
南相馬市への要望・提案事項
- ドラッグストアの設置
- 区内行事情報の一元化
- 小高駅に観光案内所の設置
- 小高駅に券売機の設置(小高駅は無人駅です)、有人化、エレベーターの設置
- 小高区と原町区の循環バス(電車は時間によっては2、3時間に1本)バスの運行無し
- 小高診療所の診療科目の増加(現在、内科と外科のみ)、特に小児科を
- 認知症対応施設の建設
- 小高区の歴史資料室の設置
これらの要望に、南相馬市 門馬市長から回答はありましたが、
人口が約3,900人の小規模の町では、採算と労働人口不足でかなえられないことが多く残念です。
でもこのような要望を直接区民が提出することが出来るということが素晴らしい創造性の第一歩だと思います。
また、昨年10月末に、「小高区まちづくりワークショップ」が浮舟文化会館で開かれ、
私も参加させていただきました。
これは官民合同ティーム主催(復興省からの役人が市に出向し、
市の地域振興課と合同で町の復興に取り組んでいる)で
小高区に在住の人や小高の町づくりに興味を持っている人を対象に募集して開催されました。
始めに趣旨説明があった後、震災後閉鎖されている県立高等学校の視察をしました。
帰りは、小高駅から2キロほど離れているので、
学校から小高駅までのメインストリートの町歩きをして町の様子を見て回りました。
そして会館に帰って、4班に分かれて話し合いを持ちました。
- 町歩きをして気づいたこと
- 県立高校の校舎を多角的に利用ができるか、どのようなものを望むか
- 昔の小高の良い所、課題と思うこと
- どんな町にしたいか など
第一回目なので、お互いの紹介をして、あまり肩ぐるしくない雰囲気で、それぞれの意見を出し合いました。
意見交換とまとめは次回に先送りとしました。
また、いつかこの続きの報告が出来ると思います。
最近、私の心を打つ言葉に出会いました。
その方は、震災原発被災後から今までの色んなお話の後に、このように言われました。
「この震災があったからこそ、素晴らしい人生を送る事が出来た、
と言えるような生き方をこれからしたい。」と。
「わたしの召命物語 -挫折-」

私も、自分の人生を振り返ってみた時、本当につらい思いをしたことや、
挫折が自分の人生を豊かにしてきたことを感謝しています。
高等学校を卒業して、直後2月末に西宮に行き、幼稚園に住み込みで先生の助手をしました。
母が娘時代に勤めていた西宮の幼稚園の園長先生からの要請でした。
夜間の大学で幼稚園教諭の資格を取る約束で行ったのですが、
「夜に若いお嬢さんを出すわけにはいかない」と断られました。
約束違反だけれど仕方がありません。
園長先生は独身の高齢の方で、大変厳しい方でした。
住み込みですから、食事の準備もしなければなりません。
私は、家では3番目の娘で、「令子はお掃除をしていなさい」と、台所の手伝いをしたことがありません。
台所の手伝いが出来るのは2番目の姉まででした。
この点で母の教育はちょっとまずかったかな?ということで、料理にはずいぶん苦労しました。
園に行ったのが年度末なので、卒園と入園のための仕事が山積みです。
保護者宛の手紙を印刷するにも、当時はガリ版刷りで、
原稿を鉄筆で書いては破れ、失敗で夜中まで奮闘しました。
若かったので頑張れたのだと思いますが、3,4時間しか眠っていなかったと思います。
福山弁で話す私を園児たちには言葉がおかしいとはやし立てられ、
ピアノが出来ないのでなかなか集まってくれず、うさぎが逃げて園長先生に叱られ、涙の出る日々でした。
実際に毎日泣いていました。
負けず嫌いの私は、「おかたづけ」と「園歌」をピアノの鍵盤を押すところを覚えて、
2,3日でその2曲だけ弾けるようになりました。
卒園式、入園式を無事に終えて、めでたし!
でも、4月の中頃、高校3年生の時の母校の社会科の先生が、
高校野球の観戦の帰りに立ち寄ってくれました。
その時の園長先生の言葉「里ごころのつく頃に会いに来る教師がいますか!」と言われ、
お茶も出せませんでした。
母にこのことを話すと「帰っていらっしゃい、あの先生のもとで今日までよく我慢できたね。」と優しい言葉でした。
そしてさっさと帰りました。
第一番目の挫折!!
今日はここまで、皆さんお元気でお過ごしください。
援助マリア修道会 南相馬修道院 北村令子
|
TOP|援助マリア会とは|援助マリア会の霊性|援助マリア信徒の会|日本の援助マリア会|世界の援助マリア会