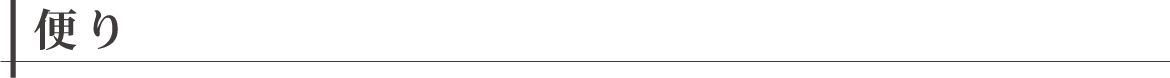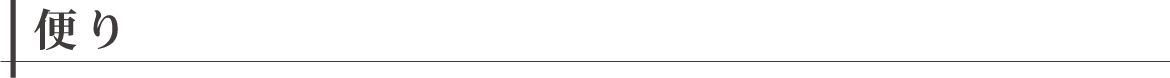
南相馬修道院からの便り
「心折れる日を超えて、再生へ向かう原発被災地小高から」
2025年、新しい年が始まって早1か月が過ぎました。
小高の町で、新たな動きが今、静かに進んでいます。
今回は、2023年9月にプロテスタントの教会で開かれた「小高夏期自由大学」という講座について紹介しましょう。
これまでにも紹介してきた「小高を愛し、小高を語る」という講座の集中講座のようなものです。
最終日には、小高の街づくりについて参加者から意見を出し合うワークショップが行われました。
そして、こんなことがあればもっと生き生きとした小高になるのではないかという意見をまとめて、
南相馬市の市長あてに提言しました。
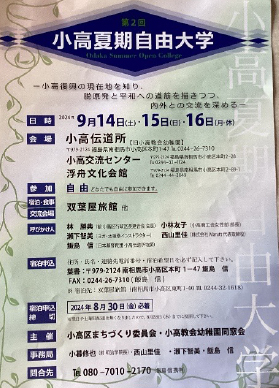 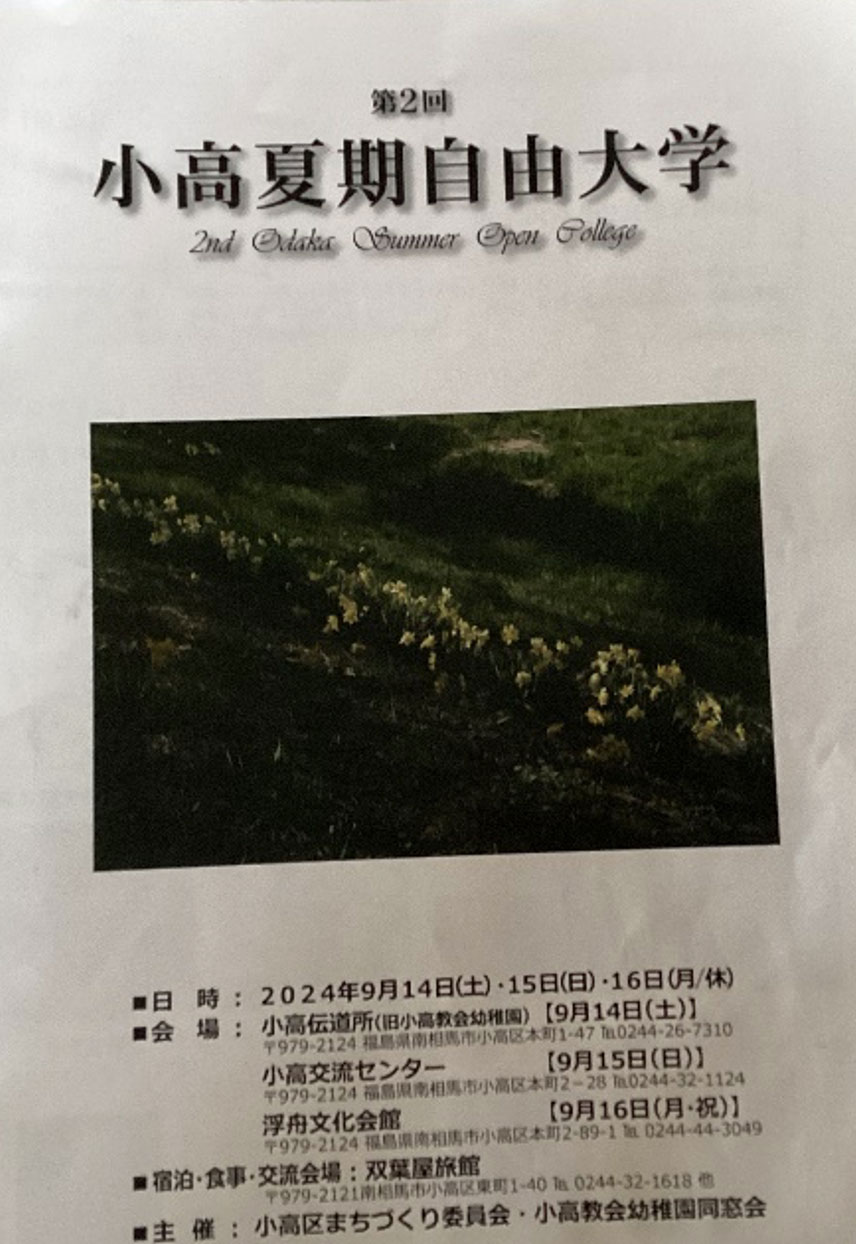
第2回目が2024年9月に開かれました。
昨年9月に2023年の講座が1冊の本にまとめられ、
「心折れる日を越え、明日を呼び寄せる」という表題で出版されました。
小高伝道所の飯島信牧師の刊行の言葉の一部を紹介します。
「この小高夏期自由大学の目的は、小高復興の現在地を知り、
脱原発と平和への道筋を描きつつ、内外との交流を深めることです」。
「心折れる日を越え、明日を呼び寄せる」
―手造りの再生へ向かう原発被災地小高からー
刊行の言葉
東京電力福島第一原子力発電所から20㎞圏内にあり、
2011年3月11日の翌日には全住民に避難指示が出され、
解除されるまでの5年間無人の街であった福島県南相馬市小高区において、
2023年9月、初めての小高夏期自由大学が開催されました。
前年10月からそれぞれ月に一度、小高伝道所を会場として行われていた住民の交流の場である
「小高への想いを語る集い」と「小高を愛し、小高を語る自由人の集い」の
総集約としての意味を持つものでした。
小高区内外から、3日間、延べ145名が参加したこの集いは、
「3.11東日本大震災」当時の様子や、その後の復興への取り組みが、
徹底して住民の目線から語られたものとして、豊かな実りを生みました。
第1日目の3人の登壇者によるパネルディスカッションでは、
被災当時、避難をめぐってどれほど大きな苦しみや葛藤があったのか、
またその経験から何を学んだのか、
さらになお解決していない課題がいくつも残されていることなどが、赤裸々に語られました。
経験した者でないと決して理解できない事柄である一方、
語らいには聴衆を包み込む温かさがありました。
第2日目の午前に行われたパネルディスカッションです。
ここでの内容は、復興という言葉より、文字通り、「地域の再生」と言う言葉こそ相応しい、
地に足の着いた取り組みが4人のパネラーによって報告されました。
忘れがたい言葉があります。企業を誘致して地域の復興を図ろうとする考えに対して語られた言葉です。
パネラーの一人は次のように発言しました。(以下は要略)
「(企業の誘致に成功しても、何かの理由で、企業が撤退したとき)こういう地域は、
ある日『突然死』してしまうというリスクをはらんでいる。
小さくてもいいから生業を、得意な事、好きな事を生かして生活する人がたくさんいて、
何か課題があればみんなで解決しようとするコムニティーには仲間が増え、活発になる。・・・」
「・・・ただ空中で意見を言うだけじゃなくて、自分の周りの半径1キロぐらいを幸せに出来るように、自分が動かなければ・・・」、
「・・・何かその地域のためではなく、自分が幸せになるために行こうと思えたのが・・・」
1日目の切実な被災体験から始まったこの集いは、2日目の若者たちによって語られた「小高再生への歩み」によって、
明日へと向かう勇気と希望を分かち合う場となりました。
後略
ぜひこの本を手に取ってお読みください。
特に基調講演の高橋哲也氏の「私たちの現在地 ― 今、世界で、福島で問われていること」は、
原発推進と軍事的背景、犠牲のシステム、安保と原発など、日本人として世界人としての、
核に対する考え方など大きな示唆を得ることができると思います。
2024年9月13日初版発行
編著者 : 小高夏期自由大学事務局
発行者 : 安田正人
発行所 : 株式会社ヨベル ISBN978-4-911054-0C0216 \1300円+税
「わたしの召命物語」

母や姉弟の捧げの心を感じて一層励まされた私でしたが、
生来のいたずら好きは修道院に入っても治りませんでした。
修道生活についての無知と、若さ(21歳で入会しました)による未熟さと無謀さで、
これまでこんな志願者は居なかったと言われるほどでした。
入会早々、修練長さまに、「穴のあいた5円玉を貸してください」と言って、
針金を弓のように曲げて輪ゴムで5円玉を真ん中にして針金とつないで、
5円玉をぐるぐるねじって、少し硬めの紙に包んで、表に『サソリの標本』と書きます。
そう〜っと開くと、バタバタっと音がしてサソリが生きているかとびっくり放り出す。
それを修練長さまにやって驚かせるなど、こんなことをしてうっ憤を晴らすのが、私の志願期の楽しみでした。
それで修練長さまが「あなたの修道名はリバデネイラ(イエズス会士でいたずら好きの聖人?)にしましょう」
と言われていたほどです。
「サソリの標本」作ってみてください!!こんな私が神様のお役に立てるのでしょうか??
神様にお出来にならないことはないようです。
今日はここまで。寒さの中、皆様 風邪などひかれないようお大事にお過ごしください!!
援助マリア修道会 南相馬修道院 北村令子
|
TOP|援助マリア会とは|援助マリア会の霊性|援助マリア信徒の会|日本の援助マリア会|世界の援助マリア会